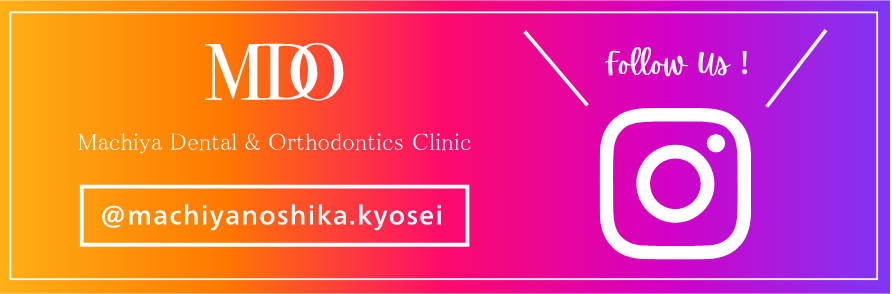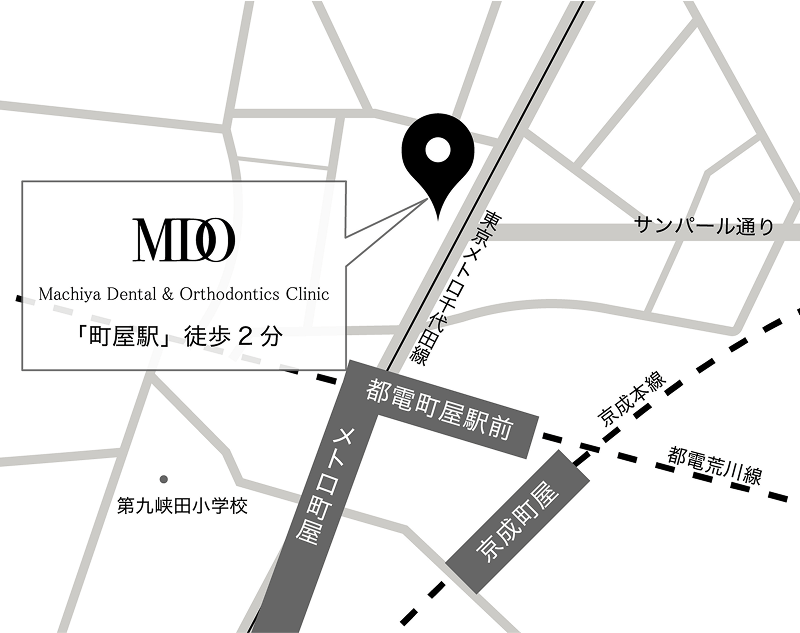「神経を取るってどういうこと?」──“もう終わり”じゃなく、そこから始まる歯の人生。
「神経を取る治療になりますね」と言われて、
「えっ、それってもうダメってことですか?」と不安な表情をされる患者さんはとても多いです。
神経を取る──それは歯にとって大きな出来事です。
でもそれは、「歯の寿命が終わった」という意味ではなく、
“その歯を残すための最後の選択”であり、“新たな管理のスタート”でもあります。
今回は、神経を取る治療の意味と、治療後に気をつけていくべきことをお伝えします。
■そもそも「神経を取る」とは?
神経を取る(=抜髄)とは、歯の内部にある神経と血管の通り道(歯髄)を除去する治療です。
通常は、
- 虫歯が深くまで進行してしまった
- 強い痛みが出てしまっている
- 神経が炎症・感染を起こしている
といった状態に対して行います。
神経を取ると痛みはなくなりますが、歯としては「生きている状態」から「構造物として残った状態」に変わるということになります。
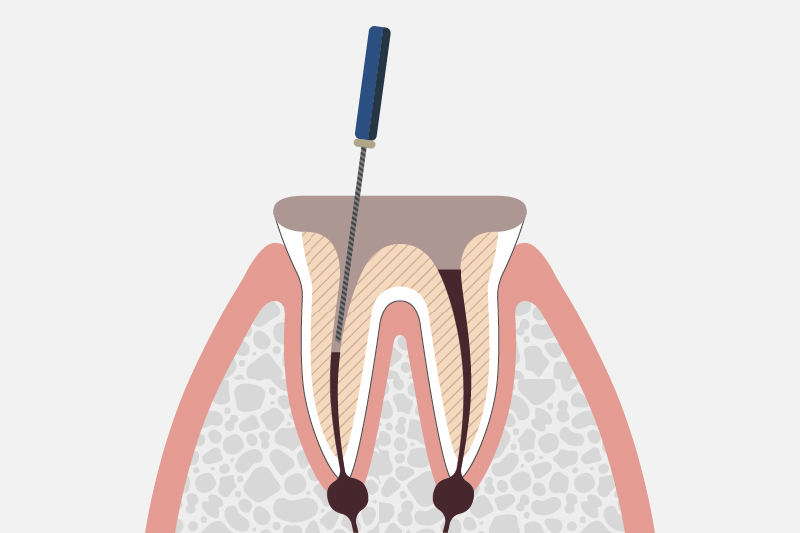
■神経を取った歯に起こる変化
神経を取った歯には、いくつかの変化があります。
◎【1】“栄養”が届かなくなる
神経と血管がなくなることで、歯が乾燥し、もろくなりやすくなります。
つまり、割れやすく・欠けやすくなるというリスクが増すのです。
◎【2】“感覚”がなくなる
熱い・冷たいなどの感覚がなくなるため、異変に気づきにくくなります。
「虫歯が進行しても痛みがない」「トラブルが起きても気づかない」ことも。
◎【3】再発リスクがゼロではない
神経を取った歯でも、根の先に細菌が再感染したり、二次虫歯になったりする可能性があります。
“もう虫歯にならない歯”ではないという点が重要です。
■なぜ「残せるなら残したい」と言われるのか?
実は、神経がある健康な歯の方が圧倒的に長持ちします。
だからこそ、歯科医師は「できれば神経を残したい」と考えるわけですが、
それでも痛みや炎症の程度によっては、取らざるを得ないこともあるのです。
そして、神経を取った歯でも、適切に治療・補強し、メンテナンスを続ければ、何年も使っていくことは十分可能です。
■治療後こそ、丁寧に守っていくことが大事
神経を取った歯に対しては、治療後の管理がとても重要になります。
- 噛む力に耐えられるように、被せ物でしっかり補強する
- すき間から虫歯が再発しないように、精度の高い治療を受ける
- フロスや歯間ブラシで周囲のプラークを徹底的に除去する
- 定期検診でレントゲンチェックを行い、内部の変化を早期発見する
このように、治療後の「使い方」や「管理のしかた」が、その歯の寿命を大きく左右します。

■まとめ:「終わり」ではなく、「これからどう守るか」
神経を取るというのは、たしかに“重大な転機”です。
でもそれは、歯を残すために必要な選択であり、未来に向けた治療です。
- 神経を取っても、すぐに抜歯になるわけではありません
- きちんと補強・管理すれば、長く使っていける可能性があります
- 治療後こそ、定期検診とセルフケアが最重要です
大切なのは、「治療が終わったから安心」ではなく、
**「ここからどう守っていくか」**という意識に切り替えること。