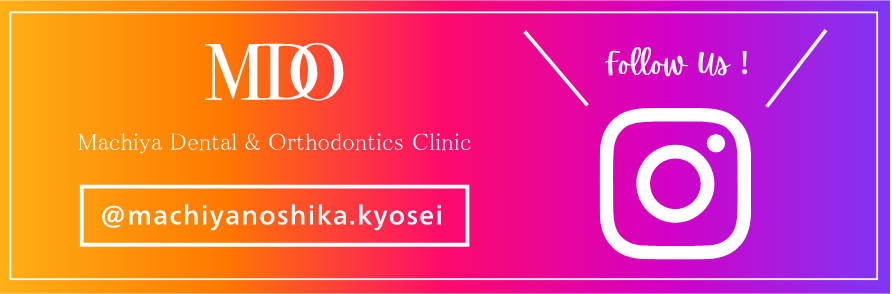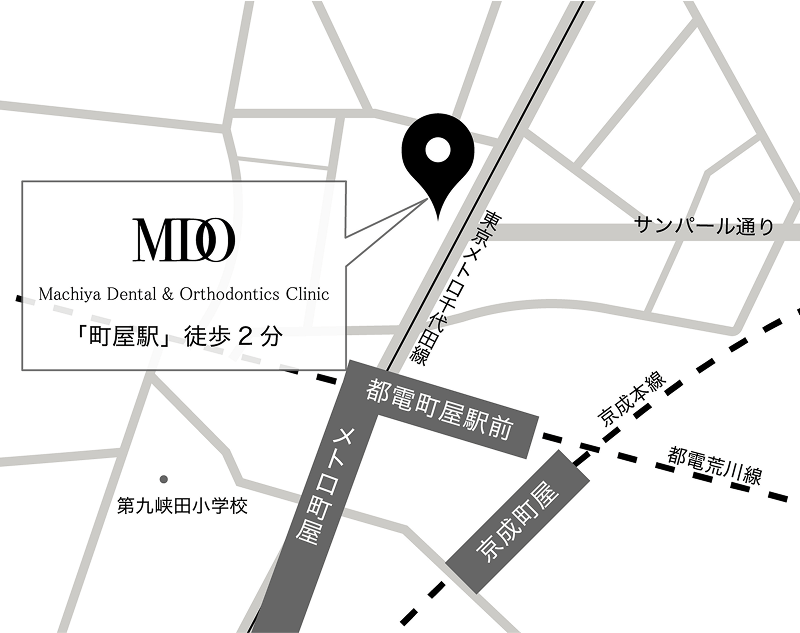「ちゃんと磨いてるのに虫歯になるのはなぜ?」──毎日磨いている“つもり”が落とし穴かも
「ちゃんと歯みがきしてるのに、なんで虫歯になったんですか?」
これは、実際の診療現場でよく聞く質問のひとつです。
1日2回、3回。毎食後にきちんと磨いている。
フロスやうがいもしている。
それでも虫歯になると、「何がいけなかったの?」と戸惑いますよね。
でも実は、“磨いている”と“汚れが落ちている”は、必ずしもイコールではないのです。
■歯みがきで虫歯は防げる…はずなのに?
もちろん、歯みがきは虫歯予防の基本です。
ただし、それは正しい方法で、正しい場所を、十分な時間をかけて磨けていることが前提です。
「磨いているつもり」でも、実際には以下のような“落とし穴”があるかもしれません。
- 同じ場所ばかり磨いて、苦手なところはいつも磨き残している
- 力が強すぎて、ブラシがすぐ広がってしまい、汚れをかき出せていない
- 歯ブラシの毛先が届きにくい奥歯や歯と歯の間は、ほとんど手つかず
- フロスや歯間ブラシを使っていないため、歯と歯の間に汚れが残っている
これでは、“毎日磨いてる”という努力が報われにくいのです。
■虫歯ができやすい“盲点スポット”がある
歯みがきで落としきれない場所は、どこか?
それは、多くの人に共通しています。
- 奥歯の噛み合わせの溝(食べかすが溜まりやすい)
- 奥歯の外側・内側(腕や口の動きで届きにくい)
- 歯と歯の間(フロスを使わないと取れない)
- 歯と歯ぐきの境目(磨きにくく、歯周病も起こりやすい)
つまり、「自分ではしっかり磨いているつもり」でも、構造的にどうしても届きにくい場所があるのです。
そしてそこにプラークが残り、少しずつ虫歯や歯周病が進行していきます。
■体質や生活習慣でも差が出る
同じように磨いていても、虫歯になりやすい人・なりにくい人がいます。
その違いは、体質的な要因や生活習慣も影響しています。
- 唾液の量が少ない(唾液には自浄作用や再石灰化の働きがある)
- 虫歯菌の種類や数が多い
- 歯の表面の質がやわらかい
- 間食の頻度が高い(特に甘い飲み物や食べ物)
こうした条件が重なると、しっかり磨いているつもりでも虫歯になることがあります。
■“痛くなってから”では、もう手遅れのことも
虫歯や歯周病は、痛くなる前から静かに進行していることがほとんどです。
「気づいたら大きな穴が空いていた」「レントゲンでしかわからなかった」——そんな声も少なくありません。
そして、痛みやトラブルを感じてから受診すると、治療が大がかりになるケースが多いのが現実です。
神経を取ったり、かぶせ物になったり、最悪の場合は抜歯になることも。
だからこそ、「何もないときに歯科を受診する」=定期健診がとても大切なのです。
■定期健診は「虫歯を見つける場」ではなく、「虫歯を作らない場」
定期健診では、ただ虫歯をチェックするだけではありません。
- 歯みがきの癖や磨き残しのチェック
- 汚れが残りやすい場所の重点クリーニング
- 歯ぐきの状態や歯周病のリスク評価
- フッ素塗布や再石灰化の促進ケア
- 必要に応じて生活習慣のアドバイス
つまり、「病気になる前に手を打つ」場所なんです。
毎日のセルフケアと、数ヶ月に一度のプロケアを組み合わせることで、虫歯や歯周病のリスクを最小限に抑えることができます。
■まとめ:「努力しているのに虫歯」がなくなる未来へ
「ちゃんと磨いてるのに虫歯になる」
その背景には、磨き残しのクセ、体質、生活習慣、そして“気づけない場所”の存在があります。
でも、だからといってがっかりする必要はありません。
定期的なプロのチェックとケアを取り入れれば、自分では気づけない部分をカバーし、歯の健康を長く守ることができるのです。
日々のケア+定期健診=最強の予防。
ぜひ「痛くなる前の受診」、「定期的なメンテナンス」を習慣にしてみてください。